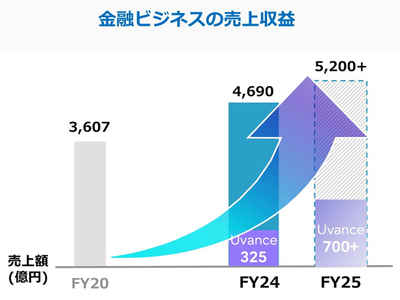【対策必至】中小企業を標的とした巧妙な「ボイスフィッシング」詐欺!28億円被害の実態と対策
2025-05-31

読売新聞オンライン
近年、中小企業を狙った「ボイスフィッシング」詐欺が巧妙化の一途を辿っており、企業に多大な被害をもたらしています。金融機関や関係者を装った電話で、偽のウェブサイトに誘導し、法人口座の情報を詐取。その結果、不正送金が発生するケースが後を絶ちません。
警察庁の取材によると、昨年11月以降、4月末までに国内約80社がこの手口で騙され、計約28億円が不正に送金されていたことが判明しました。この被害額は、今後さらに増加する可能性も示唆されており、中小企業の皆様は警戒を強める必要があります。
ボイスフィッシングの手口とは?
この詐欺の手口は、主に以下の流れで進められます。
- 電話による接触: 詐欺グループは、中小企業の担当者に電話をかけ、「システム改修」「セキュリティ強化」などの名目で、偽のウェブサイトに誘導します。
- 偽サイトへの誘導: 誘導されたウェブサイトは、本物の金融機関やサービスプロバイダーのサイトを模倣しており、一見すると区別がつきにくいほど巧妙です。
- 情報入力の誘導: 偽サイト上で、ログインID、パスワード、口座番号などの重要な情報を入力させます。
- 不正送金の実行: 入力された情報をもとに、詐欺グループは法人口座から不正に送金を行います。
中小企業が陥りやすい理由
中小企業がボイスフィッシング詐欺に陥りやすい背景には、以下の要因が考えられます。
- 担当者の知識不足: 最新の詐欺手口に関する情報が不足している場合、巧妙な手口に騙されてしまう可能性があります。
- セキュリティ意識の低さ: 大企業に比べて、セキュリティ対策が十分に行われていない場合があります。
- 電話対応の不備: 従業員が不慣れな電話に対応する場合、詐欺グループに情報を与えてしまう可能性があります。
企業が取るべき対策
ボイスフィッシング詐欺から自社を守るためには、以下の対策を徹底することが重要です。
- 従業員への教育: 最新の詐欺手口に関する情報提供や、不審な電話への対応方法に関する研修を実施しましょう。
- ウェブサイトの確認: 金融機関や関係機関からの連絡があった場合は、必ず公式ウェブサイトで情報を確認しましょう。
- 二段階認証の導入: 法人口座に二段階認証を導入することで、不正ログインのリスクを軽減できます。
- 不審なメールや電話への注意: 身に覚えのないメールや電話には、安易に対応しないようにしましょう。
- 警察への相談: 不審な電話やメールがあった場合は、速やかに警察に相談しましょう。
ボイスフィッシング詐欺は、中小企業の経営を脅かす深刻な問題です。日頃から十分な警戒心を持ち、対策を講じることで、被害を未然に防ぐことができます。今回の情報が、皆様の企業を守る一助となれば幸いです。